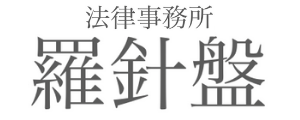法律事務所羅針盤(千葉県市川市)所属の弁護士本田真郷です。
マンションやアパート、戸建てなどの不動産を賃貸する際、「定期建物賃貸借契約(定期借家契約)」を利用するとオーナー・大家側には様々なメリットがあります。
たとえば契約期間が満了したときに確実に建物を返還してもらえるので、オーナー側に近々物件を使用する予定があっても安心して賃貸できます。
ただし定期建物賃貸借契約にはデメリットもあるので、事前に制度内容を正確に理解しておく必要があります。
今回は定期建物賃貸借契約とはどういったもので普通建物賃貸借契約と何が異なるのか、メリットだけでなく契約締結の際の注意点も含めて弁護士が解説をしていきます。
1.定期建物賃貸借契約とは?普通借家契約との一番の違い
定期建物賃貸借契約とは、マンションやアパートなど建物を借りる際の契約の種類の一つです。
オーナー・大家側が、「◯月〜◯月まで期間限定で物件を貸し出したい」という時や、「入居者に期間満了で確実に退去してほしい」というような時に利用されます。
定期借家契約の場合は、最初に決められた契約期間を満了すると借主の意向だけでは、契約が更新できずに、退去することが必要になります。
普通建物賃貸借契約の場合でも、契約期間は定めます。しかし、借主に契約の終了を希望しなければ、基本的には契約が「更新」されることとなります。
オーナー・大家側が借り主の更新を拒絶できるのは借主側の悪質な迷惑行為や家賃滞納など「正当事由」がある場合に限られ、正当事由がなければ契約は延々と更新され続けます。
数年だけなど短いスパンで物件で貸し出したい場合、安易に普通賃貸借契約を締結してしまったら、大家が使いたい時に自分の家を使えなくなる恐れがあります。
定期建物賃貸借契約であれば、定められた契約期間が終了すると、お互いが合意して再契約しない限り建物を必ず退去してもらえます。最低限の賃貸期間も特にありません。
居住用だけではなく事業用の物件にも定期建物賃貸借契約を適用できます。
「近々物件を利用したいけれどもしばらくの間は賃貸に出したい」方にとって、定期建物賃貸借契約には大きなメリットがあるといえるでしょう。
2.定期借家契約のオーナー・大家側、借り主側それぞれのメリット・デメリット
次に、定期借家契約のメリット・デメリットを大家側、借主側それぞれの視点で見ていきます。
2-1.定期借家のオーナー側メリット
1.必ず退去してもらえるし短期間でも貸し出せるので、物件を柔軟に使える
定期建物賃貸借契約を利用すると、契約期間が満了したときに必ず物件を返してもらえます。また契約期間を1年未満とすることも可能です。
たとえば近々物件を売却したい予定があるけれど、それまでの間のみ賃貸したい場合、近々子どもなどの親族に使わせたいけれどもそれまでの短期間のみ賃貸したい場合などがよくあるケースです。
このようなケースでは普通賃貸借契約は適しません。
2.賃料改定に関する特約が有効になる
普通建物賃貸借契約では、借主が強く保護されるので賃料不増額特約を定めても効果が認められず、借主による賃料減額を阻止する方法はありません。
一方、定期建物賃貸借契約であれば賃料改定に関する特約が有効となるので、借主から賃料減額を求められるリスクを低減できます。
3.立ち退き料が不要
普通借家契約の場合、契約期間が終わっても、更新が前提のため、オーナー都合で借主を退去させたい場合は、立ち退き料が必要になる場合もあります。
特に、事業用の物件などの場合は、立ち退き料も高額になりがちです。
定期借家契約であれば、期間満了で更新の義務がないので、立ち退き料不要で物件が手元に戻ってきます。
ただし、定期借家契約でも、契約期間中にオーナー都合で立ち退いて貰う場合は、立ち退き料が必要になることもあります。
2-2.定期借家のオーナー側デメリット
マンション・アパート・戸建てなど住居系の場合、家賃が相場より安くなりがち
定期借家契約は一般的に、オーナー側にメリットの多い契約になります。そのため、貸し出す際の家賃は相場より、やや低くなってしまう可能性があります。
ただ、定期借家の中でも事業用の賃貸の場合は、期間が10年など長期になるものも多いです。期間が長くなれば、借主にとっても普通借家と定期借家の違いが少なくなるため、需要のあるエリアの物件であれあば、家賃に影響しないこともあります。
2-3.定期借家の借り主側メリット
家賃が相場より安くなることが多く運がよければ掘り出し物物件に出会えることも
オーナー側のデメリットの裏返しですが、定期借家契約の場合、借主にとっては良い物件を相場より安く借りられることがあります。
定期借家契約は、最初に決められた契約期間を、借主の意向だけでは更新することができません。そのような制約がある代わりに、家賃は相場より安くなることがあります。
借主側のメリットはこれに尽きるといってもいいでしょう。
物件によっては、「いざというときのために定期借家契約にしているけど、特に問題を起こさない入居者の場合は基本的に契約更新をしてほしい」という場合もあります。
物件探しの段階で、定期借家契約の物件が気になった場合、不動産屋に契約更新ができるか確認すると、掘り出し物の物件に出会えるかもしれません。
2-4.定期借家の借主側デメリット
1.借主の意向だけで契約期間を更新できない
定期借家契約では、オーナー側の都合で物件を借りることができる期間が決まっています。そのため、「良い物件だからもっと長く住みたい!」と思ったとしても借主の意向だけでは契約期間を伸ばすことはできません。
ただし、オーナー・大家さんと合意が取れた際は、契約期間を更新することができます。
2.契約期間の途中で解約をすると残りの分の家賃を請求される可能性がある
期間の短い定期借家契約は、自分の意志で更新ができないだけでなく、退去も決まった時期でしかできないことがあります。
途中で特別な理由なく退去・解約をしてしまうと、残り分の家賃を請求されることがあるので注意しましょう。
多くの場合は、中途解約が可能な特約が定められているので、問題にならないこともありますが、契約内容の確認は事前に行うようにしてください。
中途解約の特約が定められていなかったとしても、転勤・実家の介護など正当な理由がある場合は、途中解約が可能です。
【定期建物賃貸借契約と普通建物賃貸借契約の違いの一覧表】
定期建物賃貸借契約と普通建物賃貸借契約には、更新の有無以外にもさまざまな違いがあります。以下の一覧表で両者の違いや特徴を把握しましょう。
| 定期建物賃貸借契約 | 普通建物賃貸借契約 | |
| 契約更新の有無 | 更新されない | 更新を前提としている(正当事由がないと更新拒絶できない) |
| 契約成立の要件 | 公正証書等の「書面」によって契約しなければならない 契約が更新されず期間の満了とともに契約が終了することを、契約書とは別の書面によって借主へ説明しなければならない | 口頭の契約も可能 |
| 契約期間 | 制限なし(1年未満の契約も有効) | 1年未満の契約期間を定めると「期間の定めのない賃貸借契約」とみなされる。 |
| 賃料増減額請求権 | 賃料増減額請求権が認められる 賃料改定の特約がある場合には特約が有効になる (特約は賃料額が客観的かつ一義的に定まる必要あり) | 賃料増減額請求権が認められるが、賃料増額請求権については特約で排除できる。賃料減額請求権は特約があっても排除できない。 |
| 契約終了 | 契約期間が1年未満なら特段の通知は不要。 契約期間が1年以上の場合、オーナーは期間満了の1年前から6ヶ月前までの間に借主へ期間満了により契約が終了する旨の通知をしなければならない | 期間の定めのある賃貸借の場合、オーナーは期間満了の1年前から6ヶ月前までの間に、「更新しない」旨の通知をしなければ契約が法定更新される。 通知をしても、期間満了後にテナントが建物の使用を継続していて、オーナーが遅滞なく異議を述べないと契約が更新される。 オーナーが通知するためには、6ヶ月以上の予告期間が必要で(借地借家法第27条、第30条)実際に更新を拒否するには正当事由も必要。 |
| 期間経過後の契約継続について | 継続するには、オーナーと借主が合意して再契約しなければならない | 契約の継続が前提(オーナーによる更新拒絶には正当事由が必要) |
| 期間の定めのある契約における途中解約権 | 中途解約の特約がある場合、オーナーと借主は特約に従って解約できる。オーナーからの解約申入れには、6ヶ月以上の予告期間が必要と考えられ(借地借家法第27条、第30条)正当事由も必要(借地借家法第28条、第30条)。 中途解約の特約が無い場合 原則として、オーナー、借主ともに中途解約できない。 一定要件を満たせば借主からの解約請求は可能。 | 期間の定めのある賃貸借契約で中途解約の特約がある場合、オーナーも借主も特約に従って解約できる。ただしオーナーからの解約申入れには正当事由が必要。 中途解約の特約が無い場合、オーナー、借主ともに中途解約は基本的にできない。 |
3.定期建物賃貸借契約の特徴
上述したメリット・デメリットの解説と重複する部分もありますが、借地借家法に定められている定期借家契約の法令上の特徴を解説していきます。
3-1.契約期間満了で更新されない
定期建物賃貸借契約には普通賃貸借契約と比べて以下のような特徴があります。
3-1.契約が更新されず、更新を拒否することに正当事由も不要
普通建物賃貸借契約の場合、契約期間が終わったあとも更新をすることが原則です。
オーナーが更新を拒絶できるのは正当な事由(住民の迷惑行為など)がある場合に限られ、正当事由は非常に厳格に判断されます。
オーナー側がどうしても物件を利用しなければならない事情がなければ建物の返還は受けられません。
定期建物賃貸借契約の場合には、更新されないので、正当事由がなくても期間満了によって当然に契約が終了します。
3-2.書面で契約締結しなければならない
定期建物賃貸借契約を利用する場合、必ず書面で契約しなければならず、口頭で契約した場合、普通賃貸借契約となってしまいます。
また契約時、更新されないことを説明する文書を契約書とは別に交付しなければなりません。
3-3.短期間の契約が有効
普通賃貸借契約の場合、契約期間を1年以上にしなければなりません。1年未満の契約期間を定めると「期間の定めのない契約」とみなされてしまいます。
定期建物賃貸借契約の場合、1年未満の契約も有効です。
3-4.借主からの中途解約権が認められる
中途解約権についても取り扱いも定期建物賃貸借契約と普通建物賃貸借契約に違いがあります。
期間の定めのある賃貸借契約において中途解約の特約がない場合、普通建物賃貸借契約では基本的にお互いに中途解約はできません。
一方、定期建物賃貸借契約の場合、以下の2つの条件の両方にあてはまれば借主からの中途解約が認められ、借主による解約申入れから1か月で契約が終了します。
- 居住用建物の賃貸借契約であり、契約対象の床面積が200㎡未満
かつ
- 転勤や介護、療養などのやむをえない事情によって借主が建物を生活本拠として使用するのが困難となった
借主の中途解約権を借主に不利に変更する特約は無効です。
4.定期建物賃貸借契約の注意点
定期建物賃貸借契約を利用する際には以下の点に注意が必要です。
4-1.無効になると普通建物賃貸借契約になってしまう
定期建物賃貸借契約を締結するには、書面で賃貸借契約書を作成しなければなりません。
書面には、契約を更新しない旨を明らかにする必要があります。
また契約書とは別途、契約が更新されないことを明らかにする書面をオーナー側から借主側へと交付しなければなりません。
これらの契約書作成や書面交付の要件を満たさないと、賃貸借契約が普通建物賃貸借契約となってしまいます。
そうすると、契約期間が満了しても物件を返してもらえず1年未満の契約期間も定められません。
定期建物賃貸借契約を利用するなら、必ず書面作成や交付の要件を守りましょう。
なお法律上は「公正証書等」書かれていますが、定期建物賃貸借契約の書面は一般的な契約書で足り、公正証書にする必要はありません。
4-2.オーナー側から中途解約は基本的にできない
定期建物賃貸借契約を設定すると、基本的にオーナー側からの中途解約ができません。中途解約したい場合には、当初の段階で中途解約の特約を入れておくべきです。
また居住用物件の場合、借主には一定要件を満たせば中途解約権が保障されます。
借主から完全に中途解約権を奪うのは難しいので、留意しておきましょう。
4-3.更新はできず再契約が必要
定期建物賃貸借契約では更新ができません。
契約期間の満了後も契約を締結したい場合、再契約が必要です。その際にはあらためて定期建物賃貸借契約とするのか普通建物賃貸借契約へ変更するのかなど、借主側と話し合って決めなければなりません。そのときの状況や借主との関係性により、適切な条件を定めましょう。
再度定期建物賃貸借契約を設定するなら、あらためて書面交付の要件を満たさねばならないので、忘れないようにしてください。
4-4.何度も定期借家で再契約をしていると、普通借家契約にみなされることもある
同じ借り主と何度も定期借家契約の再契約を繰り返していると、定期借家契約が認められない可能性があります。
基本的に、借り主を保護する性格の強い借地借家法の中で、貸主有利の定期借家契約はいわば「例外」のようなのものです。
何度も定期借家の再契約を結んでいると、実質、普通借家契約と大差がないにも関わらず、貸主側が「例外」を繰り返すことになるので、あまり良い方法ではありません。
具体的には、貸主側がいざ契約を終了させたいときに、それが認められないことなどが可能性として考えられます。
5.オーナー側の希望で普通借家契約を定期借家契約に切り替える方法
今までは普通借家契約で借り主と契約をしていたとしても「今の物件の建て替えを3年後に行いたいので、住人にそのときまでに退去してほしい」などの理由で、定期借家契約に切り替えが必要になることもあります。
この場合、最も円滑に話を進めるには、住人に事情を説明したうえで、現在の普通借家契約を合意の上で終了をさせ、新しく定期借家で契約を結ぶことになります。
住人が納得をしてくれればスムーズなのですが、ここがうまくいかないと、強制的に定期借家に切り替えるようなことは通常できません。
契約の切り替えができない場合は、普通借家契約のまま時期が来た時に退去交渉を行わねばならず、住人から立ち退き料など請求される可能性があります。
この交渉もうまく行かなかった場合は、裁判手続での解決を検討することとなります。
6.マンション、アパート賃貸のご相談はお気軽に弁護士へご相談ください
定期建物賃貸借契約にはメリットもデメリットもあります。迷ったときには専門知識を持つ法律家の意見を聞いておくと、安全な選択をしやすくなるでしょう。千葉県市川市の法律事務所羅針盤では不動産オーナー様へのアドバイスや借主との代理交渉などに力を入れていますので、お気軽にご相談ください。