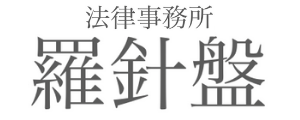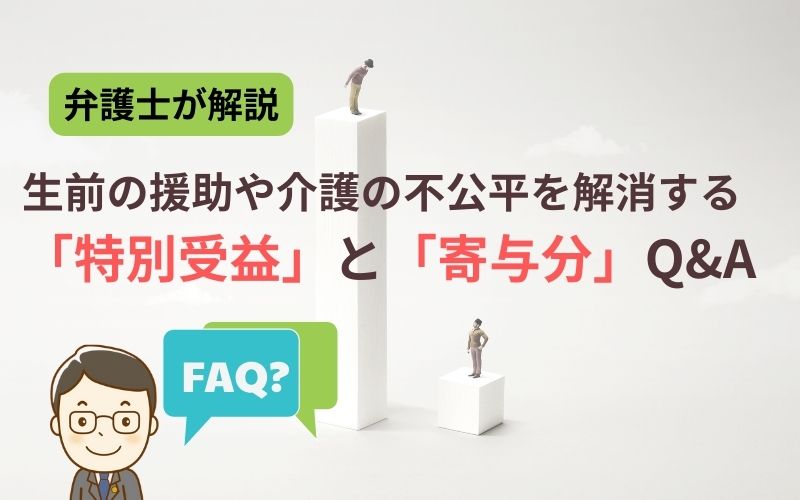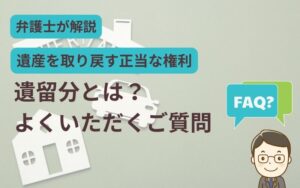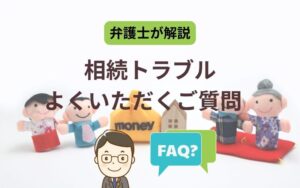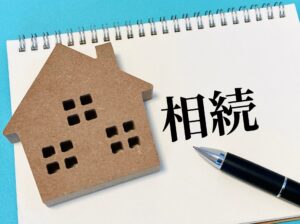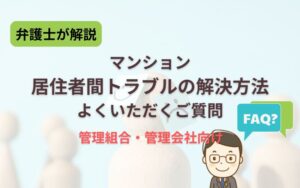- 「長男だけ、親から家を買うお金をもらっていた…」
- 「私だけが、何年も親の介護を一人で背負ってきた…」
遺産分割の話し合いの場で、このような過去の経緯から「決まっている相続分(法定相続分)で分けるのは不公平だ」と感じるケースは非常に多くあります。
法律は、こうした相続人間の実質的な公平を図るため、「特別受益(とくべつじゅえき)」と「寄与分(きよぶん)」という二つの制度を設けています。
このページでは、生前の不公平感を法的に調整するための「特別受益」と「寄与分」について、弁護士が、Q&A形式で分かりやすく解説します。
「特別受益」とは?(生前に多く財産をもらった人)
Q. 「特別受益(とくべつじゅえき)」とは、簡単に言うと何ですか?
A. 特別受益とは、一部の相続人が、亡くなった方(被相続人)から生前に受け取っていた特別な援助(贈与)のことです。
これを「遺産の前渡し」と考え、相続財産にこの金額を足し戻して(持ち戻し)から各人の相続分を計算することで、何ももらっていなかった他の相続人との不公平をなくす制度です。
Q. どのような生前贈与が「特別受益」にあたりますか?
A. すべての援助が対象になるわけではなく、遺産の「前渡し」といえるような、まとまった金額の贈与が対象となります。
- 典型的な例
- 住宅購入のための資金(頭金など)
- 事業を始めるための開業資金
- 高額な私立大学の医学部の学費など(他の兄弟と比べて突出して高額な場合)
- まとまった金額の金銭援助
- 原則として含まれない例
- 通常の生活費の仕送り
- 一般的なお小遣いやお祝い金(入学祝、結婚祝など)
Q. 「特別受益」は、相続の計算でどう扱われるのですか?
A. 相続財産に、特別受益の額を「足し戻す(持ち戻す)」計算を行います。
【具体例】
- 相続財産:4,000万円
- 相続人:長男、次男の2人(法定相続分は各1/2)
- 事実:長男は生前に住宅資金として1,000万円の援助(特別受益)を受けていた。
- みなし相続財産を計算: 4,000万円 + 1,000万円(特別受益) = 5,000万円
- 各人の相続分を計算: 5,000万円 × 1/2 = 2,500万円
- 実際の取り分を調整:
- 長男: 2,500万円(相続分) - 1,000万円(既にもらった分) = 1,500万円
- 次男: 2,500万円(相続分) = 2,500万円
もし特別受益がなければ、二人は2,000万円ずつの相続でしたが、特別受益を考慮することで、より公平な分割になります。
「寄与分」とは?(介護などで貢献した人)
Q. 「寄与分(きよぶん)」とは、簡単に言うと何ですか?
A. 寄与分とは、一部の相続人が、亡くなった方(被相続人)の財産の維持または増加に「特別な貢献」をした場合に、その貢献度に応じて、法定相続分に上乗せして財産をもらえる制度です。
- 例
- 故人の事業(家業)を無給または非常に安い給料で手伝い、財産を増やした。
- 長期間にわたり、故人の介護や看護を(無償で)行ったことで、本来かかるはずだった介護費用(ヘルパー代や施設入所費)の支出を抑え、財産を維持した。
Q. どの程度の介護をすれば「寄与分」は認められますか?
A. ここが非常に難しいポイントですが、「親族として通常期待されるレベルを超える、特別な貢献」である必要があります。
単に「身の回りの世話をしていた」「時々様子を見に行っていた」という程度では認められにくく、「介護のために仕事を辞めた」「毎日、排泄や入浴の介助まで行っていた」「その結果、介護施設費用が月〇〇万円浮いた」といった、具体的な貢献度を客観的に示す必要があります。 ハードルは低くない、というのが実情です。
Q. 寄与分を主張したい場合、どのような証拠が必要ですか?
A. 「自分がどれだけ貢献したか」を、他の相続人や調停委員・裁判官に客観的に納得してもらうための証拠が不可欠です。
- 介護の場合
介護日記、介護サービスを利用しなかったことが分かる資料、かかった費用の領収書、要介護認定の資料など。 - 家業の手伝いの場合
当時の給与明細、同業種の平均給与との比較資料、業務内容の記録など。
主張の方法と弁護士への相談の目安
Q. 「特別受益」や「寄与分」は、どうやって主張すればよいですか?
A. まずは、遺産分割協議の話し合いの場で、他の相続人に対して主張します。その際、上記のような証拠(送金履歴、介護日記など)を示しながら、なぜ公平な分割が必要なのかを具体的に説明することが重要です。
Q. 相手が認めてくれない場合は、どうなりますか?
A. 話し合いで合意できない場合は、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てます。 調停の場で、担当者として調停での話し合いを取り持つ調停委員に対し、ご自身の主張(相手の特別受益、または自分の寄与分)を証拠とともに訴えていくことになります。
Q. 弁護士への相談は、どのような場合に検討すればよいですか?
A. 特別受益や寄与分についての主張は、法的な解釈や証拠の集め方がかなり難しく、感情的な対立・衝突も生みやすいため、弁護士など専門家のサポートをうけることがおすすめです。
- 「特別受益」や「寄与分」を法的に主張したいと考え始めた時点
- どのような証拠を集めればよいか、具体的に知りたい場合
- 他の相続人が話し合いに応じず、こちらの主張を一切聞き入れてくれない場合
- 遺産分割調停を申し立てることを具体的に検討し始めた時点
弁護士は、どのような場合に法的に主張が認められやすいか、そのためにどのような証拠が有効かをアドバイスしてくれます。
また、代理人として他の相続人や調停委員に対し、法的な根拠を持って主張を組み立ててくれるため、ご自身の主張が認められる可能性を高めることができます。