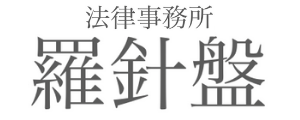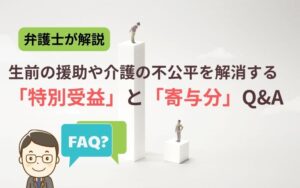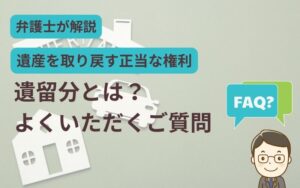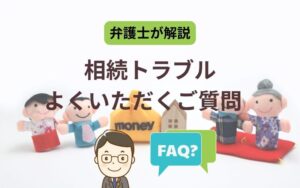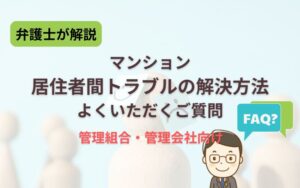前回のコラムに引き続き、本コラムでは、負動産の内、建物に関する相続の対策の必要性とその方法について解説します。
●相続対策の必要性
・固定資産税の負担
建物を相続すると、相続人が建物の所有者となるため、固定資産税が課されることになります。
土地上に建物を有している場合には、原則として土地の固定資産税は大幅な軽減を受けられますが、土地上の建物が「特定空き家」(詳しくは後述します)に指定された場合には軽減税率が適用されない場合があるため、建物の管理状態について注意する必要があります。
・権利の細分化
建物の相続が放置されると、土地と同様に、建物が多数人の共有状態になり、権利が細分化するおそれがあります。
建物に利用価値がない(すでに利用できないほどに傷んでいる)場合は安全性の観点からも解体する必要があるにもかかわらず、権利が細分化しているために所有者から必要な同意が得られず、処分が立ち行かなくなることもあるため、注意が必要です。
・相続登記の義務化
相続人には土地と同様に建物の場合も相続登記をする義務があります。
正当な理由なく登記を怠った場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
・建物周辺の環境への悪影響
建物が管理されないまま放置された場合、倒壊や資材が飛ばされるなどして、周辺の住民や建物に物理的な損害を及ぼす危険があります。
また、悪臭や景観の面でも周辺の環境に悪影響を及ぼすおそれがありますし、空き家というだけでも、犯罪者の拠点となるおそれがあるほか、ネズミ等といった野生動物やシロアリ等といった害虫の繁殖場所となるおそれもあります。
・損害賠償のリスク
倒壊したり、資材が吹き飛ばされたりして、他人の生命身体財産に対して損害を与えた場合には、建物の占有者もしくは所有者が損害賠償責任を負う可能性があります(民法717条)。
●建物の相続対策
建物の相続対策といっても、相続放棄や遺産分割といった、基本的なところは土地の場合と変わりません。
ここでは、建物特有の相続対策について解説します。
・所有権の放棄
建物についても、土地と同様に、原則として所有権を放棄することはできません。むしろ、土地とは異なり、国庫帰属制度といった制度がないことから、所有権の放棄の手段は事実上存在しないと言えます。
・所有権の消滅
建物が滅失すると、所有権も自動的に消滅することになります。この点が土地と大きく異なる点です。
財産的価値のない建物を相続してしまった場合、その後の税や管理の負担、損害賠償のリスクをなくす手段としては非常に有効な手段となります。
もっとも、建物を解体することは、建物に著しい変更を加えることに他なりませんから、他に共有者がいる場合には、共有者全員の同意を得る必要があります(民法252条の2第1項)し、解体費用を誰が負担するかをめぐってトラブルになることもあります。また、上述したように、建物が所有している土地上に建っていた場合には、建物を解体した場合、軽減税率の適用が受けられなくなり、土地の固定資産税が高くなる場合があるため、注意が必要です。
・所有権の譲渡
建物を相続した場合、土地と同様、基本的には譲渡(売却・贈与)により処分することになります。
ただし、土地と異なり、建物の場合、資産価値がないものを譲り受ける人はほとんどいませんので、なるべく価値が残存している内に売却等により処分する必要があります。
●空き家の処分
・特定空き家
建物(特に被相続人の住居)を相続する場合、その家は築古なことが多く、また、その高齢者が介護施設等に入居していたような場合には長い間適切な管理がなされていないことも多いと考えられます。
その後、相続人が適切な処分をすれば問題ありませんが、相続人の住所から遠く離れていたり、疎遠な親類の家だったりすると、誰も管理処分をしないまま空き家として放置されます。また、処分しようとしても、解体費用が捻出できない場合や、相続人間で意思統一ができない場合には放置せざるをえないこともあります。
こうして管理がなされないまま建物が放置されますと、「相続対策の必要性」で述べたようなリスクが生じることになります。
そして、その老朽化が進み、保安上の危険が生じるなど、具体的な危険が予期される段階になると、空家等対策の推進に関する特別措置法(以下、単に「法」と言います)2条2項に定める「特定空家等」に指定されます。
「特定空家等」に指定されますと、土地の軽減税率が適用されなくなり、固定資産税が増加するほか、行政により必要な措置について指導・勧告・命令がなされ(法22条)、命令に従わない場合、50万円以下の過料が課されることとなります(法30条)。なお、これらを経ても改善されない場合、行政代執行法に基づき強制的に建物の解体等がなされ、その費用を所有者が支払うこととなります。
・空き家バンクの活用
売却先を見つけるのが難しい家については、空き家バンクを活用することが考えられます。
空き家バンクは自治体やNPO法人が運営している、空き家の売買や賃貸借のマッチングを行うサービスです。登録は無料で、仲介手数料もかからないため、負担を避けるために早々に手放したいと考えている方には有用なサービスです。
●小括
建物は土地と異なり、月日が経てば経つほど財産的価値は下落し、譲渡による処分が難しくなります。また、老朽化した空き家を放置すると、民事上の損害賠償や行政上の処分等が科されるおそれがあります。
空き家バンク等のサービスを活用しつつ、早めに処分することを心がけた方が良いでしょう。
●弁護士に依頼するメリット
ご家族が介護施設に入り、家の管理ができていない場合やすでに使用していない家の相続をしてしまった場合等、今後発生する可能性のある家の相続の問題から、現在発生している家の相続の問題まで、相続に関する経験豊富な弁護士が的確なアドバイスをすることができます。
また、ご希望に応じて、遺言の作成や他の相続人との交渉等といった具体的なサポートを行うことができます。
ぜひ一度、弁護士にご相談ください。
(執筆者 弁護士 大月裕哉)