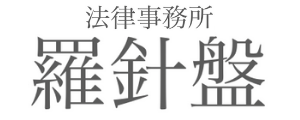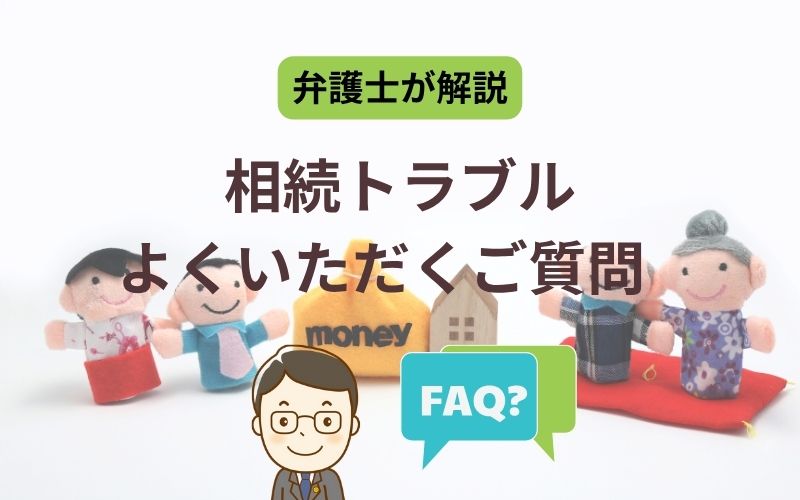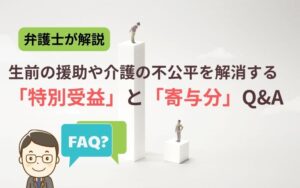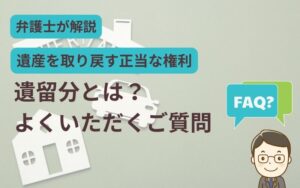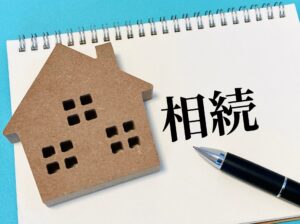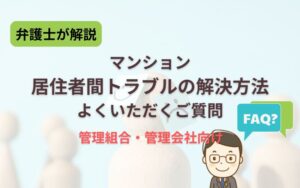「他の相続人と意見が合わない」
「感情的になってしまい、話し合いにならない」
相続が発生した多くの方が、遺産分割協議(遺産の分け方を決める話し合い)で壁にぶつかります。大切なご家族を亡くされた中で、相続人同士が対立してしまうのは、精神的にも辛い状況です。
話し合いがまとまらない場合、状況の応じて法的な対応を検討していくことになります。
このページでは、遺産分割で揉めてしまった時にどうすればよいのか、その具体的な解決策をQ&A形式で分かりやすく解説します。
まず知っておきたい遺産分割基本の知識
Q. そもそも「遺産分割協議」って何ですか?
A. 遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ)とは、亡くなった方(被相続人)が遺した財産を、誰が、何を、どのくらい相続するのかを、相続人全員で話し合って決める手続きのことです。
銀行預金の解約や、不動産の名義変更(相続登記)といった手続きを進めるには、この話し合いで全員が合意したことを証明する「遺産分割協議書」という書類が必要になります。つまり、相続手続きを進めるための、最初の、そして最も重要なステップがこの話し合いなのです。
Q. 話し合いには誰が参加しないといけないのですか?
A. 法律で定められた相続人(法定相続人)全員が参加し、全員が合意する必要があります。一人でも欠けていたり、無視して進めたりした遺産分割協議は無効になってしまいます。
例えば、「長年疎遠だったから」「仲が悪いから」といった理由で特定の相続人を外すことはできません。まずは戸籍謄本などを取り寄せて、誰が法的な相続人になるのかを正確に確定させることが、話し合いのスタートラインとなります。
Q. 遺産分割の話し合いに期限はありますか?
A. 遺産分割協議そのものには、「いつまでに終えなければならない」という法律上の明確な期限はありません。
ただし、相続税の申告と納税には、「相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内」という期限があります。遺産分割がまとまっていないと、税金の軽減措置(配偶者控除など)が使えず、本来より多くの税金を納めなければならなくなる可能性があります。そのため、一つの目安として10ヶ月以内に協議をまとめることを目指すのが一般的です。
遺産分割の話し合いが進まない時の具体的な対応
Q. 相続人の一人が、話し合いに全く応じてくれません。どうすればよいですか?
A. 遺産分割は、相続人全員の合意が大原則です。そのため、話し合いに参加しない相続人を無視して手続きを進めることはできません。
相手が感情的になっている、あるいは遠方に住んでいるなど、直接の対話が難しい場合は、まずは手紙などで冷静に「遺産分割を進めたいので、協力してほしい」という意思を伝えてみましょう。それでも全く応じてもらえない場合は、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立て、法的な場で話し合うことを検討します。
Q. 不動産など、分けにくい財産はどうやって分けるのですか?
A. 相続財産に不動産が含まれていると、分割方法で意見が対立しやすくなります。法律では、主に以下の3つの分割方法が定められています。
- 現物分割(げんぶつぶんかつ)
土地を分筆してそれぞれが相続するなど、財産そのものを分ける方法。 - 代償分割(だいしょうぶんかつ)
相続人の一人が不動産をすべて相続する代わりに、他の相続人に対して、その人の相続分に相当するお金(代償金)を支払う方法。 - 換価分割(かんかぶんかつ)
不動産を売却して現金に換え、その現金を相続分に応じて分ける方法。
どの方法が最適かは、それぞれの相続人の希望や状況によって異なります。全員が納得できる方法が見つからない場合は、これも「調停」で話し合う議題となります。
Q. 話し合いがまとまったら、何をするのですか?
A. 全員の合意が得られたら、その内容を「遺産分割協議書」という正式な書面にまとめます。この書類は、後々のトラブルを防ぐための契約書のようなもので、相続人全員が署名し、実印を押印します。
この遺産分割協議書と印鑑証明書などをセットにすることで、初めて銀行で預金を解約したり、法務局で不動産の名義を変更したりといった、具体的な相続手続きが可能になります。
遺産分割トラブル法的な解決のステップ
Q. 話し合いで解決しない場合、次はどうなるのですか?
A. 当事者同士での解決が難しい場合、「遺産分割調停(いさんぶんかつちょうてい)」という手続きを利用します。これは、家庭裁判所で、調停委員という中立的な立場の専門家を交えて、再度話し合いを行う場です。
調停は、裁判のように勝ち負けを決める場所ではありません。 あくまで、調停委員がそれぞれの相続人から個別に事情を聞き、法的なアドバイスをしたり、解決案を提示したりしながら、全員が納得できる合意点(妥協点)を探っていく話し合いの場です。非公開で行われるため、プライバシーも守られます。
Q. 調停でも話し合いがまとまらなかったら、どうなりますか?
A. 調停で合意に至らなかった場合(調停不成立)、手続きは自動的に「遺産分割審判(いさんぶんかつしんぱん)」に移行します。
審判では、もう話し合いは行われません。各相続人が提出した資料や主張に基づき、裁判官が、法律に則って「このような方法で遺産を分割しなさい」という最終的な決定(審判)を下します。これは、野球の審判が「ストライク!」と判定するのに似ています。 審判で下された決定には法的な強制力があり、原則として、全員がその内容に従わなければなりません。
遺産分割協議 弁護士など専門家への相談の目安
Q. 遺産分割協議がまとまらないとき、弁護士への相談は、どのような場合に検討すればよいですか?
A. 弁護士への相談は、ご自身の権利を守り、精神的な負担を軽減するために有効な選択肢です。特に、以下のような状況では、専門家の助言を得ることが円滑な解決につながります。
- 相続人の一人が話し合いを完全に拒否しており、交渉の糸口が見えない時点
- 相続人同士の関係が悪化し、冷静な対話が不可能な場合
- 家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てることを具体的に検討し始めた時点
- 他の相続人が提示する分割案が、法的に見て妥当なのか判断できない場合
- 不動産や自社株など、評価や分割が難しい財産が含まれている場合
- 他の相続人が財産を隠している可能性がある場合
弁護士に依頼すると、代理人として他の相続人との交渉窓口になってくれるため、直接やり取りするストレスがなくなります。
また、法的な観点から、ご自身の状況における妥当な解決策や見通しを知ることができます。