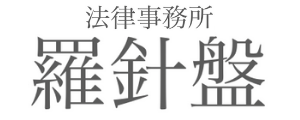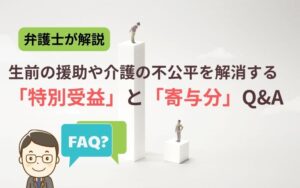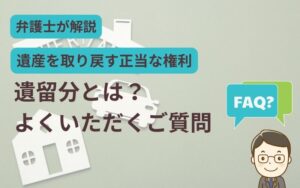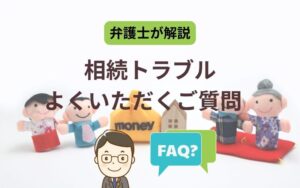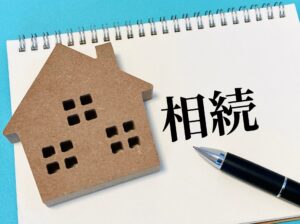相続は、多くの方にとって一生に何度も経験するものではありません。そのため、「何から手をつけていいかわからない」「家族と揉めてしまったらどうしよう」といったご相談をよくいただきます。このページでは、相続手続きの基本から、トラブルになりやすい遺産分割、遺留分、相続放棄など、皆様からよく寄せられるご質問に弁護士が分かりやすくお答えします。
相続開始直後の手続きについて
Q. 家族が亡くなりました。何から始めればよいですか?
A. まずは以下の3つを期限内に進める必要があります。
- 死亡届の提出(7日以内): 故人の死亡地または本籍地、届出人の所在地の役所に提出します。
- 遺言書の有無の確認: 自筆の遺言書を見つけた場合、家庭裁判所で「検認」という手続きが必要です。勝手に開封しないようご注意ください。公正証書遺言の場合は検認は不要です。
- 相続人の調査・確定: 故人の出生から死亡までの戸籍謄本等を取り寄せ、誰が法的な相続人になるのかを確定させます。
これらの手続きと並行して、相続財産の調査も進めます。ご自身で進めるのが難しい場合は、初回相談からサポートいたしますので、お早めにご相談ください。
Q. 相続人の調査は、なぜ必要なのでしょうか?
A. 故人に離婚歴や認知した子がいる場合など、ご家族が把握していない相続人が存在する可能性があるためです。もし相続人の一部を除外して遺産分割協議を行っても、その協議は無効となってしまいます。後々のトラブルを防ぐためにも、戸籍等に基づく正確な相続人調査は非常に重要です。
Q. 相続登記が義務化されたと聞きました。どういうことですか?
A. 2024年4月1日から、不動産(土地・建物)を相続したことを知った日から3年以内に、法務局で名義変更の手続き(相続登記)を行うことが法律で義務付けられました。正当な理由なくこの義務を怠った場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。過去に相続した不動産で、まだ名義変更が済んでいないものも対象となりますので、心当たりのある方はすぐにご対応ください。
Q. 相続税の申告は、必ず必要ですか?
A. いいえ、必ずしも全員が必要なわけではありません。相続財産の総額が、基礎控除額を超える場合にのみ、申告と納税が必要です。 基礎控除額の計算式は「3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)」です。 例えば、相続人が3人の場合、基礎控除額は4,800万円です。遺産総額がこの金額以下であれば、相続税の申告は原則として不要です。申告期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内です。
遺産分割・遺留分について
Q. 遺産分割協議とは何ですか?
A. 相続人全員で、「誰が」「どの財産を」「どれくらいの割合で」相続するのかを話し合って決める手続きです。全員の合意が得られたら、「遺産分割協議書」という書面を作成します。この協議書は、不動産の名義変更(相続登記)や預貯金の解約手続きの際に必要となる重要な書類です。
Q. 話し合いがまとまりません。どうすればよいですか?
A. 相続人間での話し合いが難しい場合は、弁護士が代理人として交渉に入ることが可能です。感情的な対立を避け、法的な根拠に基づいて冷静に交渉を進めることで、解決への道筋が見えることが多くあります。それでも合意できない場合は、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立て、調停委員を交えて話し合いを進めることになります。
Q. 「特別受益」や「寄与分」とは何ですか?
A. どちらも、相続人間の公平を図るための制度です。
- 特別受益: 相続人の中に、故人から生前に多額の贈与(住宅資金、開業資金、結婚式資金など)を受けていた人がいる場合、その贈与額を遺産に加算して各人の相続分を計算します。
- 寄与分: 故人の財産の維持や増加に特別な貢献(長年の介護、事業の手伝いなど)をした相続人がいる場合、その貢献度に応じて相続分を増やすことができる制度です。 これらの主張をする場合は、具体的な証拠に基づいて交渉や法的手続きを進める必要があります。
Q. 「遺留分」について、もっと詳しく教えてください。
A. 遺留分とは、兄弟姉妹を除いた「法定相続人」に保障された、最低限の遺産の取り分のことです。たとえ遺言書に「全財産を特定の一人に相続させる」と書かれていても、他の相続人は自分の遺留分を主張できます。これは、故人の意思を尊重しつつも、残された家族の生活を保障するための制度です。
Q. 私の遺留分は、具体的にいくらになりますか?
A. 遺留分の割合は、法定相続人が誰かによって決まります。
- 配偶者のみ、または配偶者と子(または孫)が相続人の場合:法定相続分の2分の1
- 親(または祖父母)のみが相続人の場合:法定相続分の3分の1 個別の計算は複雑になるケースも多いため、正確な金額については弁護士にご相談ください。
Q. 遺留分を請求したいのですが、どうすればよいですか?
A. まずは、遺留分を侵害している相手方(多くの遺産を受け取った相続人など)に対して、「遺留分侵害額請求」を行う意思表示をします。トラブルを避けるため、後から「言った・言わない」とならないよう、内容証明郵便で送付するのが一般的です。相手が話し合いに応じない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。
Q. 遺留分の請求に期限はありますか?
A. はい、非常に重要な期限があります。遺留分を請求する権利は、以下のいずれかの期間が経過すると時効によって消滅します。
- 相続の開始と、遺留分を侵害する贈与や遺贈があったことを知った時から1年
- 相続開始の時から10年
「知った時から1年」は非常に短いため、遺言書の内容に納得がいかない場合は、できるだけ早めに弁護士などの専門家へご相談ください。
Q. 生前によくわからずに「遺留分を放棄する」という念書にサインさせられました。これは有効ですか?
A. いいえ、相続が開始する前に(被相続人が亡くなる前に)行われた遺留分の放棄は、法的に無効です。たとえ念書に署名・捺印していても、遺留分を請求する権利は失われません。遺留分の放棄が法的に有効となるのは、相続開始後に、家庭裁判所で所定の手続きを行った場合に限られます。
Q. 生前に受けた贈与も、遺留分の計算に関係しますか?
A. はい、関係します。遺留分を計算する際の基礎となる財産には、被相続人が亡くなった時の財産だけでなく、一定期間内に行われた生前贈与も含まれます。これにより、亡くなる直前に特定の相続人にだけ財産を集中させて、他の相続人の遺留分を不当に減らすといった行為を防ぎます。
相続放棄・限定承認について
Q. 故人に多額の借金がありました。相続しないといけませんか?
A. いいえ、相続しない方法があります。「相続放棄」という手続きを家庭裁判所で行うことで、プラスの財産(預貯金や不動産)もマイナスの財産(借金)も、両方とも一切引き継がないで済みます。相続放棄は、原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」に手続きをする必要があります。
Q. 借金がいくらあるか分かりません。どうすればよいですか?
A. プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いか不明な場合は、「限定承認」という手続きを検討します。これは、相続したプラスの財産の範囲内でのみ借金を返済し、もし財産が残ればそれを引き継ぐことができる制度です。ただし、手続きが複雑で、相続人全員で共同して行う必要があります。どちらを選択すべきか、まずは弁護士などの専門家にご相談ください。
遺言書について
Q. 遺言書は書いた方がよいのでしょうか?
A. はい、ご自身の意思を確実に実現し、残されたご家族間のトラブル(いわゆる「争続」)を防ぐために、作成しておくことを強くお勧めします。特に、相続人同士の仲が良くない場合や、相続人以外の人に財産を渡したい場合などには遺言書の重要性が高まります。
Q. 遺言書にはどのような種類がありますか?
A. 主に「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があります。
- 自筆証書遺言: 全文を自分で手書きする遺言書。手軽ですが、形式の不備で無効になったり、紛失や改ざんのリスクがあります。
- 公正証書遺言: 公証役場で公証人に作成してもらう遺言書。費用はかかりますが、形式不備の心配がなく、最も確実で安全な方法です。
弁護士へのご相談・費用について
Q. 相続問題で弁護士に依頼するメリットは何ですか?
A. 弁護士にご依頼いただくことで、以下のようなメリットがあります。
- 手続きを代行してもらえる:面倒で時間のかかる戸籍収集、財産調査、遺産分割協議書の作成などをすべて任せられます。
- 法的なアドバイスを受けられる:ご自身の状況で、法的にどれくらいの権利があるのか、どう交渉すれば有利に進められるか、的確なアドバイスを受けられます。
- 精神的な負担が軽減される:他の相続人との交渉窓口を弁護士に一本化することで、直接やり取りするストレスから解放されます。
Q. 弁護士費用はいくらかかりますか?
A. ご相談内容やご依頼いただく業務の範囲によって異なります。当事務所では、ご契約前に必ず費用について詳細な見積もりをご提示し、ご納得いただいた上で手続きを進めます。初回相談の際に、費用の概算についてもお気軽にお尋ねください。(詳しくは、こちらの相続問題の弁護士費用ページをご確認ください。)
上記以外のご質問や、ご自身の状況に合わせたより具体的なアドバイスをご希望の場合は、どうぞお気軽に当事務所の【無料】初回相談をご利用ください。