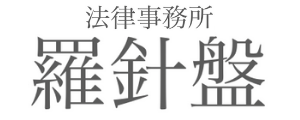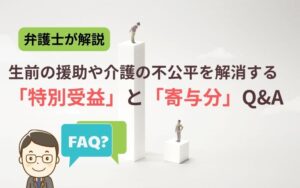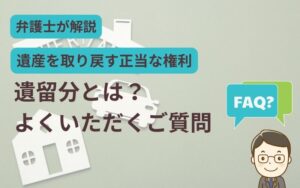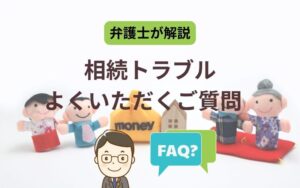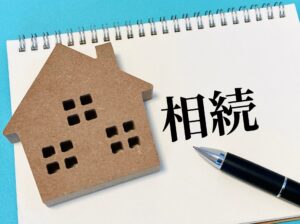1 寄与分制度(民法904条の2)とは
⑴ 制度の考え方
ある相続人が、被相続人の扶養や介護、事業等を引き受けたことにより、被相続人の財産の維持や増加に貢献したと言えるような場合に、相続において、その相続人の相続分を他の相続人よりも有利に扱う制度です。
例えば、被相続人を自宅で介護し続けた相続人がいた場合、その相続人は本来、被相続人を介護施設に入所した場合に費消していたであろう財産を守ったといえるのであり、そのような財産については、その相続人に相続分を優遇することで還元しようとする仕組みです。
⑵ 法律上の仕組み
寄与分を主張したい相続人は、相続開始後に行われる遺産分割協議の際に、妥当な相続分について、他の相続人と協議して決めることとなります。
もっとも、他の相続人にしてみれば、寄与分を認めることはすなわち、自己の相続分が減少することになりますから、当事者の話し合いではまとまらないことも少なくありません。
そこで、相続人間の話し合いでまとまらない場合には、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立て、裁判所を交えて話し合いをします。その際に、寄与分を主張したい相続人は、その旨を主張することになります。
それでも決まらない場合には、審判手続に移行し、裁判所が寄与分やその他の諸般の事情を考慮して、裁判所が決めることになります。(ただし、当事者はこれに対して裁判所に不服申し立てをすることができます。)
2 特別寄与料制度(民法1050条)とは
こちらは、2019年の民法改正により新設された制度です。
制度の考え方は寄与分制度と同じですが、寄与分はあくまで「相続人」の相続分を増やす制度であるのに対し、こちらは、相続人を除く「被相続人の親族」に適用される制度です。被相続人と深く関わる可能性があるものの、相続の対象外となる方への適用が想定されています。
特別寄与料制度は寄与分制度とは異なり、適用者は寄与度に応じた額を特別寄与料として、相続人に対し請求することができます。
3 寄与分制度の要件
⑴ 「相続人」であること
一つ目の要件として、被相続人の相続人であることが必要です。友人や知人はもちろん、親族であっても被相続人に子や孫がいる場合の被相続人の父母きょうだいや、被相続人の配偶者等は寄与分の対象とはなりません。
ただし、特別寄与料制度においては、相続人以外の被相続人の親族(※)に適用があります。
※親族とは、六親等内の血族、配偶者三親等内の姻族を指します(民法725条)。
⑵ 被相続人の財産の維持または増加に寄与したこと
二つ目の要件として、被相続人の「財産」の「維持または増加」に貢献したことが必要です。
例えば、被相続人の看護をしたとしても、被相続人の精神面でのケアにとどまった場合や、被相続人の事業を手伝った場合にも、結果として事業が失敗に終わり、財産が減少した場合、被相続人を介護したとしても、被相続人から介護料に相当する金銭を収受していた場合には認められません。
⑶ 特別の寄与であること
寄与分が認められるためには、法的に要求される通常の貢献を超えた特別の貢献が必要です。
民法上、親族間、夫婦間については、互助義務や扶養義務が規定されています(親族については民法730条、夫婦については民法752条)。親子間については監護義務が規定されています(民法820条)。したがって、これらの義務の範疇で行った行為については、「特別の」貢献とまでは言えません。
具体的には、要介護でない高齢の親と同居し、その親の食事を作り、日々の世話をしたという程度では特別の貢献とまでは認められない可能性があります。
4 寄与分制度のハードル
この通り、寄与分が認められるためには、要件の段階で高いハードルが設けられています。
特に、「特別の寄与」に当たるといえるかは難点であり、自身では多大な労力を費やし、特別の寄与に当たるという確信があった場合でも、裁判所はこれを認めない場合も少なくありません。
また、実際上のハードルとしても、寄与分は遺言に対して劣後するため、遺言に反する寄与分を主張することはできません。
そのため、実際に寄与分が認められるケースは少ないものとなっています。
5 寄与分が適用される場面
主に適用が考えられるケースとして想定されるのは次のケースが挙げられます。
①介護が必要な被相続人を、施設に預けずに自宅で介護したケース
②被相続人の事業を無償で手伝ったケース
③被相続人の財産を無償で管理したケース
いずれのケースも無償、あるいはそれに準ずるような低額の報酬であることが前提であり、かつ、多大な費用や労力を必要とするものです。
6 寄与分を主張するためには
相続人に寄与分を主張するためには、要件を充足していることを主張するだけで足りる場合もあります。
しかし、裁判所に権利を認めてもらうためにはそれだけでは足りません。自分の貢献が相続人の財産を維持または増加させた特別の寄与であることを、書類等によって証明する必要があります。
親族間の付き合いですから、例えば、契約書といった形で書類を残すことは難しいと考えられます。
そこで、将来、寄与分の主張をしたいと考えている方は、後々に備え、一人だけでも作成できる日記や家計簿を付けておくことが有効です。
すでに被相続人が死亡し、相続が開始した後であっても、被相続人の通帳や、親族間や業者とのやり取りのメール、被相続人のための買い物時のレシートを集めておくなど、自分の貢献の度合いを証明しうるような証拠をできる限り集めておくことを心がけましょう。自身の貢献を証言してもらえるような親族を味方につけておくこともよいでしょう。
7 寄与分の問題を避ける
もっとも、上記のように、日記や家計簿を付けるといった準備をしていたとしても、必ずしも寄与分が裁判所に認められるとは限りません。前述のように、寄与分が認められるハードルは非常に高いものとなっています。
そこで、自分の労力を評価してもらうためには、やはり、被相続人に公正証書遺言を作成してもらうことや、遺贈をしてもらうことが確実です。被相続人にお金のことを伝えると軋轢を生みかねないと考える方は多いと思いますが、良好な関係を維持し、被相続人の死後の親族間の紛争を避けるためであることを丁寧に説明するなど、被相続人に直接相談することも視野に入れましょう。
8 弁護士に相談するメリット
寄与分を主張したいと考えている方は、無償で被相続人に尽くしてきたという思いがあり、相続の場において、他の相続人と感情的な対立が起こることが想定されます。弁護士に相談することで、弁護士が依頼者と他の相続人との間に入って交渉し、感情的な対立を避けつつ、依頼者の利益を最大化すべく働きかけることができます。
また、訴訟になってしまった場合にも、依頼者の立場に寄り添った、適切な法的主張や集めるべき証拠についてのアドバイスを受けることができます。お困りの場合は、ぜひ弁護士にご相談ください。
(執筆者 弁護士 大月裕哉)