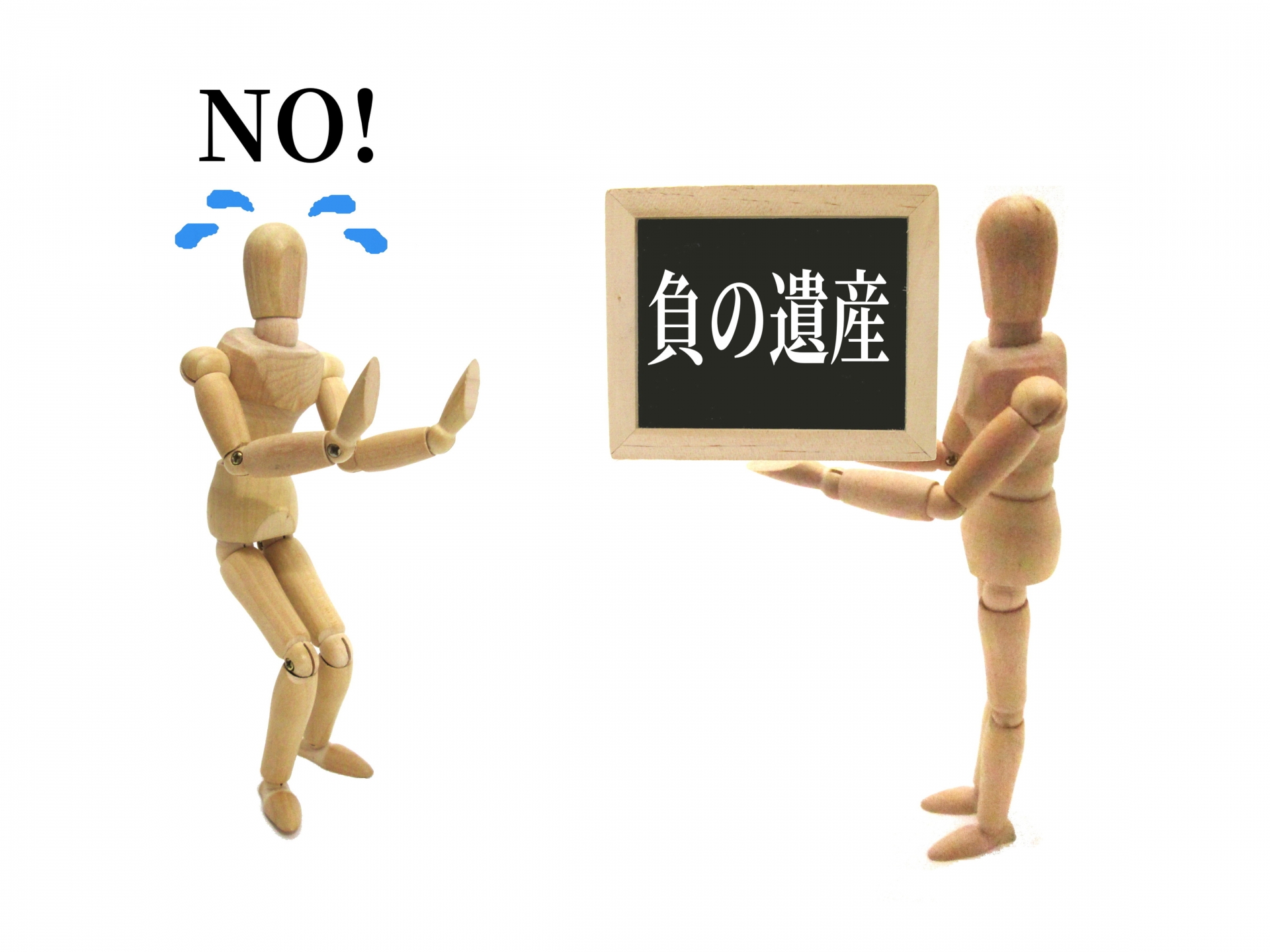法律事務所羅針盤(千葉県市川市)所属の弁護士本田真郷です。
今回は、相続開始後3か月を経過した場合の相続放棄の可否について説明します。
1 相続放棄ができる期間
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に相続の放棄をすることができます(民法915条1項)。
この3か月の期間のことを相続の承認又は放棄の熟慮期間といいます。
2 相続放棄の熟慮期間の起算点
原則
熟慮期間の起算点は、「自己のために相続の開始があったことを知った時」です。
具体的には、①相続人が相続開始の原因たる事実(被相続人の死亡等)及び②これにより自己が法律上相続人となった事実の双方を知った時から熟慮期間は進行するものとされています。
熟慮期間が進行しない場合
そのため、相続人が上記①または②のいずれかを知らないうちは熟慮期間は進行しません。
例えば、
・被相続人と疎遠で被相続人死亡の連絡を受けていない場合(①を知らない場合)
・先順位相続人(子など)がいるため、自分は相続人ではないと思っていた後順位相続人(兄弟姉妹など)が先順位相続人の相続放棄により相続人となったものの、この相続放棄の事実を知らなかった場合(②を知らない場合)
などは熟慮期間は進行しません。
この場合は、①及び②の双方を知ったときから3か月以内であれば相続放棄が可能です。
3 本来の熟慮期間の3か月を経過しても相続放棄ができる場合
(1)熟慮期間の起算点の例外
それでは、被相続人が死亡し、かつ、自分が相続人であることを知ってから3か月を経過した場合、相続放棄は不可能となってしまうかというと必ずしもそうではありません。
例えば、被相続人には相続財産が何もないと信じていたものの、相続発生の1年後に被相続人が多額の借金を抱えていたことが判明した場合などは相続放棄を行うことができる可能性あります。
この点について、最高裁昭和59年4月27日判決は、相続人が本来の熟慮期間内に相続放棄をしなかったことのが「被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続人において右のように信ずるについて相当な理由があると認められるときには、相続人が前記の各事実(筆者注:上記①②の事実)を知った時から熟慮期間を起算すべきであるとすることは相当でないものというべきであり、熟慮期間は相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時から起算すべきものと解するのが相当である」と判示しています。
つまり、上記最高裁判決により、相続財産が全くないと誤信したことに相当の理由があるなど特別な事情がある場合には、相続人が相続財産の全部又は一部を認識したとき(またはこれを通常認識し得る時)から3か月以内は、相続放棄が可能との判断が示されているのです。
「民法915条1項本文が相続人に対し単純承認若しくは限定承認又は放棄をするについて3か月の期間(以下「熟慮期間」という。)を許与しているのは、相続人が、相続開始の原因たる事実及びこれにより自己が法律上相続人となった事実を知った場合には、通常、右各事実を知った時から3か月以内に、調査すること等によって、相続すべき積極及び消極の財産(以下「相続財産」という。)の有無、その状況等を認識し又は認識することができ、したがって単純承認若しくは限定承認又は放棄のいずれかを選択すべき前提条件が具備されるとの考えに基づいているのであるから、熟慮期間は、原則として、相続人が前記各事実を知った時から起算すべきものであるが、相続人が右各事実を知った場合であっても、右各事実を知った時から3か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかったのが、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続人において右のように信ずるについて相当な理由があると認められるときには、相続人が前記の各事実を知った時から熟慮期間を起算すべきであるとすることは相当でないものというべきであり、熟慮期間は相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時から起算すべきものと解するのが相当である。」
最高裁昭和59年4月27日判決
相続放棄申述受理は比較的柔軟~相続放棄の審理構造~
相続放棄申述受理の実務は比較的柔軟に行われています。
これは裁判所における相続放棄の審理構造が影響しているためと思われます。
家庭裁判所における相続放棄の申述受理は、相続人による適式な申述がされたことを公証する機能を有するにとどまると考えられており、相続放棄の有効無効を確定する裁判ではありません(福岡家裁昭和44年11月11日審判参照)。
そのため、現在の家庭裁判所においては、通常、相続放棄の申述を却下すべきことが明らかな場合以外は、相続放棄の申述を受理すべきとの運用がとられています(東京高裁平成22年3月8日決定参照)。
「相続放棄の申述の受理に関する審判は、相続放棄の有効無効を確定する裁判ではなく、単に相続放棄の意思表示を受領し、これが相続人の真意に基づくものであることを公証する機能を有するに止まるものであり、また、この審判に伴う国家の後見的機能も相続人保護(相続人の錯誤の防止等)のために発揮されるべきことが期待されているに止まり、相続債権者保護の機能までも担っているものではないと解するのが相当である。」
福岡家裁昭和44年11月11日審判
「相続放棄の申述がされた場合、相続放棄の要件の有無につき入念な審理をすることは予定されておらず、受理されても相続放棄が実体要件を備えていることが確定されるものではないのに対し、却下されると相続放棄が民法938条の要件を欠き、相続放棄したことを主張できなくなることにかんがみれば、家庭裁判所は、却下すべきことが明らかな場合以外は、相続放棄の申述を受理すべきであると解される。」
東京高裁平成22年3月8日決定
ただし、家庭裁判所によって相続放棄の申述が受理されたからといって、これにより相続放棄の有効性が確定するわけではありません。
相続放棄の有効性は最終的には訴訟手続の結果により確定されます。
例えば、被相続人に対して貸金債権を有していた相続債権者は、相続放棄の申述を行った相続人に対し、貸金返還請求訴訟を提起し、その訴訟手続において、相続放棄の申述が無効であることを争うことが可能となります。
(2)本来の熟慮期間経過後の相続放棄に関する裁判例
上記の運用がなされていることから、少なくとも相続放棄の申述受理段階では、相当程度柔軟に受理が認められる傾向があります。
①被相続人名義の不動産があることを認識していたものの、被相続人の生前から当該不動産を他の相続人が取得する旨の相続人間の合意があった場合に、相続人には当該不動産が相続の対象となる遺産であるとの認識はなかったとして相続放棄の申述受理が認められた事例(仙台高裁平成7年4月26日決定)
相続放棄の申述時期:相続開始から約1年9か月後
「上記事実によれば、抗告人らは、被相続人の生前から、被相続人名義の不動産の一切を長男が取得することで合意していたものであって、被相続人の死亡後も、当然にその合意のとおり長男に権利が移転するものと考え、自らが取得することとなる相続財産は存在しないものと考えていたことが窺えるのであって、「相続分不存在証明書」はその手続のために用いられたに過ぎないものというべきであるから、抗告人らにおいては、被相続人の死亡により、被相続人名義であった不動産が相続の対象となる遺産であるとの認識はなかったもの、即ち、被相続人の積極財産及び消極財産について相続の開始があったことを知らなかったものと認めるのが相当である。」
仙台高裁平成7年4月26日決定
②相続人が被相続人名義の遺産の存在を認識していても、その遺産は他の相続人が相続するため、自己が相続すべき遺産がないと信じ、かつそのように信じたとしても無理からぬ事情がある場合には、相続放棄の申述が認められるとして、相続放棄の申述を却下した原審審判が破棄差し戻された事例(名古屋高裁平成11年3月31日決定)
相続放棄の申述時期:相続開始から約5年11か月後
「相続人が被相続人の死亡時に、被相続人名義の遺産の存在を認識していたとしても、たとえば右遺産は他の相続人が相続する等のため、自己が相続取得すべき遺産がないと信じ、かつそのように信じたとしても無理からぬ事情がある場合には、当該相続人において、被相続人名義であった遺産が相続の対象となる遺産であるとの認識がなかったもの、即ち、被相続人の積極財産及び消極財産について自己のために相続の開始があったことを知らなかったものと解するのが相当である。」
名古屋高裁平成11年3月31日決定
③相続人が相続財産の存在は知っていたものの、他の相続人に全財産を相続させる旨の遺言が存在した場合に、当該相続人が自身は相続財産を全く承継することがないと信じ、かつ、このように信じたことについて相当な理由がある場合は相続放棄の申述が認められるとして、相続放棄申述を却下した原審判が破棄差し戻された事例(東京高裁平成12年12月7日決定)
相続放棄の申述時期:相続開始から約4年10か月後
「抗告人は、自らは被相続人の積極及び消極の財産を全く承継することがないと信じ、かつ、このように信じたことについては相当な理由があったのであるから、抗告人において被相続人の相続開始後所定の熟慮期間内に単純承認若しくは限定承認又は放棄のいずれかを選択することはおよそ期待できなかったものであり、被相続人死亡の事実を知ったことによっては、未だ自己のために相続があったことを知ったものとはいえないというべきである。」
東京高裁平成12年12月7日決定
④相続人間で遺産分割協議を行い、不動産の相続登記を行ったものの、その後に多額の相続債務があることが判明した場合、相続債務の存在を認識せず行われた遺産分割協議が錯誤により無効となる可能性があるとして、法定単純承認事由の存在を理由に相続放棄申述を却下した原審判が破棄差し戻された事例(大阪高裁平成10年2月9日決定)
相続放棄の申述時期:相続開始から約6か月後
「抗告人らが前記多額の相続債務の存在を認識しておれば、当初から相続放棄の手続を採っていたものと考えられ、抗告人らが相続放棄の手続を採らなかったのは、相続債務の不存在を誤信していたためであり、前記のとおり被相続人と抗告人らの生活状況、他の共同相続人との協議内容の如何によっては、本件遺産分割協議が要素の錯誤により無効となり、ひいては法定単純承認の効果も発生しないと見る余地がある。」
大阪高裁平成10年2月9日決定
(3)当裁判所における相続放棄案件の取扱いに関する所感
当事務所にご依頼をいただく相続放棄案件のおよそ3分の1程度は本来の熟慮期間を経過しているケースです(弁護士への相談案件ですから、何らかの問題があるケースが多くなる傾向はあります)。
なかには相続放棄の可否に多少懸念を抱く案件がある場合もありますが、現在の家裁実務を前提とする限り、本来の熟慮期間を経過してしまったことについて相当な理由があり、かつ、その理由をしっかり説明することができれば、本来の熟慮期間経過後であっても、相続放棄のハードルはそれほど高くないとの肌感覚を持っています。
また、相続放棄の申述受理後についても、明確な相続財産処分行為等がない限り、相続債権者も比較的寛容に相続放棄を受け入れてもらえる傾向にあり、相続放棄の有効性を争われるケースは稀という感覚です。
とはいえ、本来の熟慮期間経過後の相続放棄申述は、やはり例外的に許容される位置づけであり、家庭裁判所や債権者への初期対応を間違ってしまうと取り返しのつかない状況になりかねません。
裁判例においても相続放棄の申述書提出後、家庭裁判所から受領した照会書に不用意な記載をしてしまったために相続放棄申述が却下されてしまった事例も散見されます(秋田家裁平成5年5月17日審判(仙台高裁秋田支部平成5年11月4日決定の原審))。
本来の熟慮期間経過後の相続放棄については、それなりの説明対応が必要となるため、できる限り専門家に相談し対応されることが望ましいでしょう。
4 熟慮期間の伸長
積極及び消極の相続財産の調査のため、3か月の熟慮期間内に相続放棄の当否が判断しきれない場合などは、家庭裁判所の審判により熟慮期間を伸長することができます(民法915条1項ただし書き)。
熟慮期間の伸長申立てにもそれなりの理由は必要ですが、当事務所での取扱い経験上、3か月程度の伸長であれば比較的緩やかに認められる傾向です。
本来の熟慮期間経過後の相続放棄はあくまで例外的な位置づけであり、できる限り本来の熟慮期間内に相続放棄の判断を行うべきですから、相続財産の調査状況によっては熟慮期間の伸長を積極的に検討しましょう。
相続手続きの全体像は下記の記事でも解説しています
はじめての方にとって相続手続きは、複雑に感じることが多いと思います。
下記の記事では相続手続きの全体像を初心者の方でもわかりやすいよう簡単にまとめておりますので、ぜひ参考にしてください。