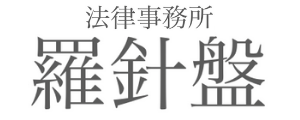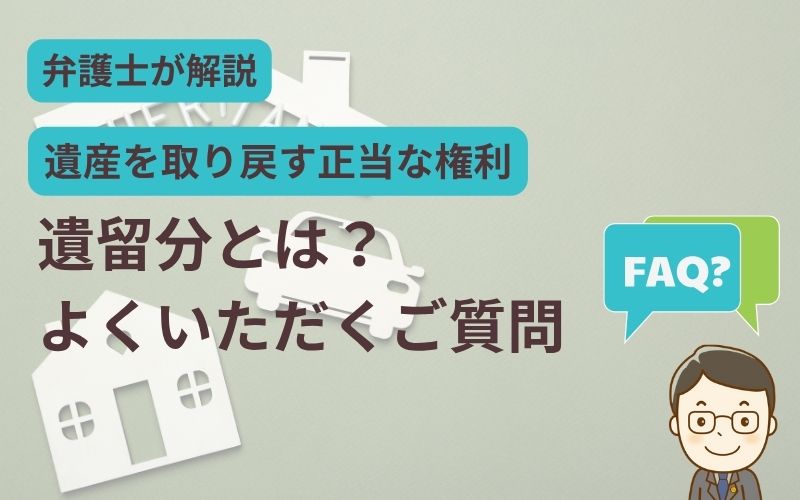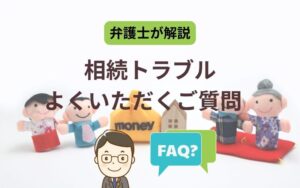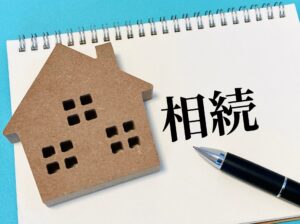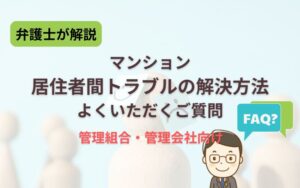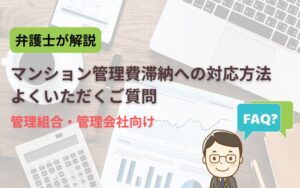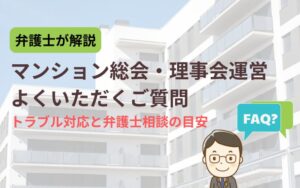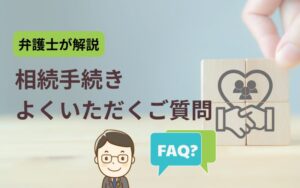「全財産を長男に相続させる、という遺言書が見つかった…」
「亡くなった父が、愛人に全財産を遺贈する内容の遺言を遺していた…」
遺されたご家族にとって、あまりにも不公平な内容の遺言書は、今後の生活に対する大きな不安をもたらします。
法律は、そのような場合に備え、残された家族の生活を保障するための強力なセーフティネットとして「遺留分(いりゅうぶん)」という権利を定めています。
このページでは、遺言書の内容に納得がいかない時に、ご自身の正当な権利である「遺留分」とは何か、どうすれば取り戻せるのかを、Q&A形式で徹底解説します。
「遺留分」とは?まず知っておきたい3つの基本
Q. そもそも「遺留分」とは、一言でいうと何ですか?
A. 遺留分とは、一言でいうと「相続において、残された家族のために法律上保障された、最低限の遺産の取り分」のことです。
故人の「誰に財産を遺すか」という意思は遺言によって尊重されますが、それによって配偶者やお子様が生活に困るような事態を防ぐため、法律が「この最低ラインだけは、必ず相続する権利がありますよ」と定めている、いわば「相続のセーフティネット」です。
Q. 誰が、どれくらいの遺留分をもらえますか?
A. 遺留分の権利があるのは、兄弟姉妹以外の法定相続人です。具体的には、配偶者、子(または孫)、親(または祖父母)です。 遺留分の割合は、相続財産全体に対して以下の通りです。
- 配偶者や子が含まれる場合 → 相続財産全体の 1/2
- 親のみが相続人の場合 → 相続財産全体の 1/3
この全体の割合を、法定相続分に応じて按分したものが、各人の具体的な遺留分となります。 例えば、相続財産6,000万円を妻と子供2人が相続する場合、遺留分として保障される合計額は3,000万円(6,000万円×1/2)となり、妻が1,500万円、子供が各750万円を受け取る権利があります。
Q. 遺留分を主張するのは、故人の意思に反するようで気が引けます…。
A. そのお気持ちは、非常によく分かります。しかし、遺留分は、故人の意思をないがしろにするための制度ではありません。故人の意思を尊重しつつも、残された家族のその後の生活基盤が揺らぐことがないようにという、法律の配慮によって認められた正当な権利です。 ご自身の今後の生活を守るために法律が認めた権利であり、非難されるべき行為ではないのでご安心ください。
あなたの遺留分はいくら?具体的な計算方法
Q. 遺留分を計算する「基礎となる財産」は、どのように決まるのですか?
A. これは非常に重要なポイントです。遺留分の計算基礎となる財産は、亡くなった時に残っていた財産だけではありません。
故人が亡くなる前に行った一定期間の「生前贈与」も、遺産に加算して計算します。これを「特別受益」と呼びます。これは、亡くなる直前に特定の相続人にだけ財産を贈与して、他の相続人の遺留分を不当に減らすことを防ぐためのルールです。
- 相続人への贈与
原則として、相続開始前の10年間に行われたものが対象 - 相続人以外への贈与
原則として、相続開始前の1年間に行われたものが対象
Q. 借金などマイナスの財産も計算に含まれますか?
A. はい、含まれます。遺留分の計算は、預貯金や不動産といったプラスの財産から、借金などのマイナスの財産を差し引いた純資産を基礎として計算されます。 したがって、もし多額の借金が残されている場合は、遺留分として請求できる金額が少なくなるか、ゼロになることもあります。
Q. 生命保険金や死亡退職金は、遺留分の計算対象になりますか?
A. 原則として、これらは遺留分の計算の基礎となる財産には含まれません。 生命保険金や死亡退職金は、受取人として指定された人の「固有の財産」とされ、相続財産とは別物として扱われるのが一般的です。ただし、特定の相続人だけに著しく高額な保険金が渡るなど、相続人間で極端な不公平が生じる場合は、例外的に財産に含めて計算されることもあります。
「遺留分」を取り戻すための具体的な手続き
Q. 遺留分を取り戻したい場合、まず何をすればよいですか?
A. 多くの財産を受け取った相手方に対して、「遺留分侵害額を請求します」という意思表示を行います。 この意思表示は、後から「言った・言わない」というトラブルを防ぐため、配達証明付きの内容証明郵便で行うのが最も確実で安全です。この請求は、裁判などを起こす必要はなく、まずは相手方との話し合い(交渉)で解決を目指します。
Q. 遺留分の請求に期限はありますか?
A. はい、あります。これが遺留分で最も注意すべき点です。
遺留分を請求する権利は、 「相続の開始と、遺留分を侵害する遺言や贈与があったことを知った時から1年間」 この期間内に行使しないと、時効によって権利が消滅してしまいます。 遺言書の内容を知って悲しんでいる間に、あっという間に1年が過ぎてしまうケースは少なくありません。納得がいかないと感じたら、まず行動を起こすことが何よりも重要です。
Q. 相手方が話し合いに応じない場合は、どうなりますか?
A. 内容証明を送っても相手が支払いを拒否したり、無視したりする場合は、家庭裁判所に「遺留分侵害額の請求調停」を申し立てます。 これは、裁判官や調停委員という中立的な専門家を交えて、解決に向けた話し合いを行う手続きです。それでも合意に至らない場合は、最終的に「訴訟(裁判)」で決着をつけることになります。
遺留分に関して弁護士に相談をする目安
Q. 遺留分の請求は、自分一人でもできますか?
A. 内容証明郵便の作成や相手方との交渉など、ご自身で行うことも不可能ではありません。 しかし、遺留分の計算には、不動産の評価や生前贈与の調査など、専門的な知識が必要な場合が多く、正確な請求額を算出するのは非常に困難です。また、感情的になりがちな親族間の交渉は、精神的な負担も計り知れません。
Q. 弁護士に相談・依頼する客観的なメリットは何ですか?
A. 弁護士に相談・依頼することには、以下のような客観的なメリットがあります。
- 正確な遺留分の計算: 財産調査や評価を行い、法的に妥当な請求額を正確に算出できます。
- 交渉の代理: 精神的負担の大きい相手方との交渉を、すべて代理人として行ってくれます。
- 法的に適切な手続きの実行: 期限内に内容証明郵便を確実に送付し、その後の調停や訴訟への移行もスムーズに進められます。
- 時間的・精神的負担の軽減: 複雑な手続きや交渉から解放され、ご自身の生活に集中できます。
特に「1年」という厳しい時効があるため、遺言書の内容に疑問を感じた時点で、一度専門家の話を聞いてみることは、ご自身の権利を守る上で非常に有効な選択肢となります。